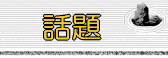 |
||
| 小野 浩美 | ||
|
No.27
|
|
|
発行者:ジャパ・ベトナム事務局
発行日:2004年 4月15日 |
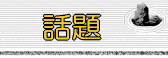 |
||
| 小野 浩美 | ||
3月15日、経団連会館でJICA主催の情報公開シンポジウムが開かれた。インフラODAの新しい時代を迎えて「社会基盤整備分野における開発援助の経験と展望」というのがそのテーマである。定員400人の会場を埋めたのは、ほとんど企業のビジネスマンのように見えた。 これまで日本のODAは、現地の実情に合わない箱物だけを作ってきただの、地元住民の生活を破壊してきただの、自然環境を破壊してきただの、様々な批判を受けてきた。それらの批判をふまえてインフラ支援の中身を捉え直し、アジア・アフリカの国々との関係で新たに戦略として位置づけていこうということのようだ。“人々の希望を叶えるインフラへ”という何とも美しい言葉が、イメージ用語として使われている。 外務省の資料によると、日本はベトナムに対し1992年以降経済協力を再開し、現在は最大の援助国で、2002年度の援助成約額は、円借款、無償援助、技術協力合わせて総額924億円である。ちなみに、日本からの対越累積投資額は2001年まで約35.2億ドル(第4位)、2002年は約1.02億ドルである。 これらベトナムに流れ込む金が、住民の生活を左右するほどの大きな力として作用していることは明らかだと思う。これらの力によって起きてくる様々な社会的変化に対して、草の根支援グループとしてベトナムに関わる私たちは、あくまで住民の生活の目線から問題を見つめていく必要があると思う。 |
対ベトナムODA見直し作業の中心メンバーであった大野氏はシンポジウムの中で、3年前オーストラリアの支援でメコン川前江に架けられた橋のことを話した。「オーストラリアは橋を造った後に住民の移転問題の調査を行い、それを自国の教科書で教材として使っている。それに引き替え、日本は一体何をしているのかと言いたい」 前江をまだフェリーで渡っていた頃、フェリー乗り場の近くには乗客相手のお店がたくさんあり、物売りが大勢車に群がっていた。橋の工事が着々と進むの目の前にして、フェリーの客相手に生計を立てているこれらの人々は、橋が完成した時はどのように生活していくのだろうと気にかかった。オーストラリアがどのような調査をし、どのように教材として使っているのか、是非知りたいものだと思う。
|
|||||||
去年の9月にカオバンを訪問した時、ハノイからカオバンに至る国道の大々的な拡張工事が進められているのを見て、沿道に暮らしていた人々がどうなったか、気にかかったままでいる。その人々に私が聞き取り調査をするのは不可能だが、ハノイに住む知り合いとその話をしたり、カオバン病院の先生達に、工事によってカオバン内がどう変化したかなどの話を聞くことはできるだろう。今年のツアーに行く時の自分の課題にしようと思う。
ホーチミン市のバイクラッシュは年々ひどくなっている。まとまった金がなければバイクを買うことはできないから、バイクラッシュはホーチミン市民の金回りがよくなったしるしと言えなくもない。排気ガスもものすごく、路地から大通りにでると空気のにおいが変わる。ホーチミン市の活気は好きだが、ここにずっと住みたくはないなと私は思ってしまう。みんな気休めのようなマスクをして走っているが、いずれ健康問題が出てきて、せっかく稼いだ金を今度はせっせと医者につぎ込まなければならなくなるのではないだろうか。 政府も対策に頭を痛めているようで、路線バスの使用を奨励したり、バイク新規登録をストップしたり、生産を規制したりあの手この手だが、なかなか効果は上がらないようだ。ベトナムを訪問したある日本人が、市内バスは2000ドン(約15円)で市内の何処へも行けて便利とホームページでおすすめしていたが、これは観光客の話。バイクを自分の足とする便利さになれきった市民は、今更路線バスに切り替えられないらしい。ラッシュで動かないバイクの横を、歩道に乗り上げてバイクを走らせている人がいたという話を聞いた時は、そのしたたかさに思わず苦笑させられた。 政府の上からの対策がお手上げならば、市人民委はここは一つ住民大会でも開催し、この事態をどう思うか、どうしたらよいと思うか、とことん皆で意見を出し合う場を設けたらいかがなものか。住民がバイクラッシュについて考えるよい機会にもなるだろう。自分と違う他者の意見に耳を傾ける中でしか、状況を変えていく道筋は見えてこない。そこで、自分の足としてのバイクが大事だからラッシュも仕方ないというところに落ち着けば、それもまたいたしかたあるまい。 |
ストリートチルドレンをサポートするグループ・タオダンの責任者だったフンさんが、責任者を退き他の人に業務を引き継いだという話が、風の便りで届いた。去年タオダンを訪問した時、彼は体調が悪く休みをとっていて私たちは彼に会うことができなかった。一途に路上の子ども達を世話してきたフンさんは今、どのような気持ちでいるのだろうか。 ストリートチルドレンも経済成長の波をかぶり、一生懸命靴磨きなどの仕事をして頑張るより、盗みをしたり、人にもらった方が早いという傾向が、以前よりも増しているという話も聞く。2005年までに路上の子どもを一掃しようという政府の政策によって、施設に入れられる子どもも増えている。タオダンは、これからますます、様々な難しい問題に直面せざるをえなくなると思われる。日本にいる私たちにできることは多くはないが、伴走者として彼らに寄り添っていく気持ちだけは、持ち続けようと思う。
自衛隊のイラク派遣に賛成する意見の中に、「現地の平和を回復するために派遣は必要」という意見がある。大上段から平和の美しい装いを振りまいているが、現地で頻発するテロ活動はそれに対する「ノー」という答えではないのか。テロ活動をしている側も住民であり、ならず者集団とは思えない。一方で「歓迎している」と言っても、一方でこんなあからさまな拒否があるなら、速やかに退去するしかあるまい。こんなところで「テロに屈しない」と粋がってどうする。 ODAであれ派遣であれ、地元住民に拒否されたら、それを押してまでして他国に足を踏み入れることはできないし、またその意味もない。それが国と国との最低限の原則ではないか。それは人と人の関係でもしかりである。
|
|||||||